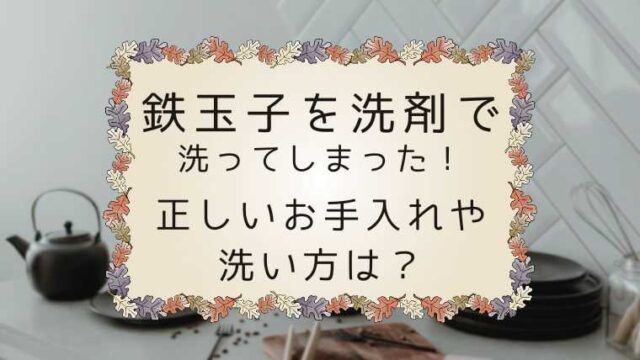墓地や街角でお地蔵様を目にしたことがある方も少なくないでしょう。
お地蔵様は仏教の彫像の一部で、一般的には寺院内にある堂々とした仏像とは異なり、公共の場所でよく見かける、親しみやすい存在です。
意外なことに、「お地蔵さんには手を合わせない方が良い」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。
もちろん、全てのお地蔵様にこれが当てはまるわけではありません。
お地蔵様も様々なタイプが存在し、中には手を合わせて敬うことが許されているものと、そうでないものがあるのです。
それでは、どのお地蔵様に対して手を合わせてはいけないのか、その理由は何なのか、興味がわきますよね?
今回は、一見するとよく知られているようであまり知られていない「お地蔵さん」に焦点を当て、詳しく説明します。
Contents
実は手を合わせてはいけないお地蔵様が存在する?

災害からの保護や、幸福をもたらしてくれる、または人々の代わりに災難を受け止めてくれると言われるお地蔵様。
しかし、その中には敬うために手を合わせるべきでないと言われるものも存在するのです。
これには理由があるのか、あるいは単なる都市伝説なのか。
その真相に迫りたいと思います。
(1)孤立したお地蔵様
一般的に、予期せぬ場所にぽつんと立つお地蔵様に対しては、軽々しく手を合わせない方が良いと言われています。
これは特に、人が少ない道や手入れされていないほこらなどでよく言われています。
管理がなされていないお地蔵様が置かれている背景には、次のような理由が一般的です。
・交通事故などで命を失った人の魂を慰める
・身寄りがない故人を供養する目的
・亡くなった子供の魂を保護する
これらは供養の目的で設置されているものが多く、故人だけでなく、不安を抱えた霊が寄り添うこともあると言われています。
そうしたお地蔵様に手を合わせると、不安な霊が自分に取り憟すことがあるという噂があります。
ただの言い伝えかもしれませんが、管理が明らかでないお地蔵様には手を合わせずに通り過ぎるのが賢明でしょう。
(2)墓地近くのお地蔵様
墓地周辺にあるお地蔵様も、先程と同様、手を合わせるべきでないとされています。
特に、誰を供養しているのか不明なお地蔵様には、控えるのが良いでしょう。
墓地は元々、霊が集まるとされている場所です。
そのため、悪い霊が近くにいる可能性も否定できません。
ただ、墓地の中にきちんと整備されているお地蔵様には、手を合わせても問題ないでしょう。
墓地にあるお地蔵様は、この世とあの世を繋ぐ存在として、故人を見守り、墓地を守る役割があると言われています。
(3)赤い装束をまとったお地蔵様
赤いよだれかけや帽子を着けているお地蔵様にも、軽い気持ちで手を合わせるべきでないとされています。
子供の姿を模したお地蔵様は、早く亡くなった子供と関連が深いです。
江戸時代に人気だった話に、親を早くに亡くした子供が三途の川で石を積み、その度に鬼によって崩されるというものがあります。
そんな子供たちを救済するのが、お地蔵様です。
早くに亡くなった子供、生まれてこなかった子供のために設置されたお地蔵様に対して、生半可な気持ちで手を合わせることは避けるべきでしょう。
手を合わせてもいいお地蔵さんもいるの?

神聖な場所や墓地の近くにあって、定期的に整備されている、管理者がはっきりとわかるお地蔵さんには、敬意を表して手を合わせても大丈夫とされています。
神社や寺院に安置されているお地蔵さんは、霊的な悪影響からその場を守る存在として設置されていることが多いです。
以下、手を合わせても安心なお地蔵さんについて詳しく説明します。
(1)地域の子供たちを守るお地蔵さん
たとえ道端にあっても、定期的に世話が行き届いているお地蔵さんには感謝の気持ちを表して手を合わせても大丈夫です。
特に関西地方では、8月に地域のお地蔵さんを称える「地蔵盆」というイベントが開催され、地域の人々が花やお供え物を持ってお地蔵さんに感謝の意を示します。
そんな愛されているお地蔵さんには、地蔵盆でない時でも敬意を表しても良いと考えられています。
(2)手入れが行き届いている墓地のお地蔵さん
墓地にも、早くに亡くなった子供や、未だこの世に生まれてこなかった魂を供養するためのお地蔵さんがあります。
管理が怠られている場合、手を合わせることに躊躇が生まれるかもしれませんが、手入れがきちんとなされている場所のお地蔵さんには、敬意を示して手を合わせても問題ないと言われています。
お地蔵さんへの敬意の表し方

お地蔵さんの拝み方
特定のお地蔵さんに手を合わせても問題ない場合、その拝む方法に厳格なルールはありません。
手を合わせ、目を閉じ、故人への感謝や思いを心の中で伝えるのが一般的です。
ただ、寺や神社の本堂内にあるお地蔵さんに参拝する際は、その場所の慣習や作法に従って行動する必要があり、例えば、二礼二拍手一礼の作法が必要な場合もあるでしょう。
一方、そういった形式に縛られない場合は、お賽銭を投げる、線香を手向ける、または花やお菓子をお供え物として捧げても良いとされています。
不明確な点があれば、訪問前に確認すると良いです。
お地蔵さんへ捧げる花の選び方
お地蔵さんに花を供える際は、刺があるものや香りが強すぎるものは避けるのが賢明です。
これには厳密な規則はないものの、刺のある花は攻撃的なイメージがあるため、また、訪れる人々に強い香りが不快に感じられる可能性も考慮する必要があります。
派手さよりも、持ちの良い、清潔感のある花を選ぶと、お地蔵さんに対する敬意をより適切に表現できるでしょう。
お地蔵さんとは何か? その起源や背景
「お地蔵さん」とは、仏教で広く信仰される地蔵菩薩を指します。
親しみやすい言葉として「お地蔵様」とも称されます。
多くの人が日本独自の存在と認識しているかもしれませんが、その起源は古代インドに遡ります。
サンスクリットでの名称は「クシティ・ガルバ」であり、それは「大地の胎内」という意味を持っています。
地蔵菩薩は、その温かな慈悲の心で、すべての人々を優しく包み込んでくれる存在とされています。
また私たちを様々な苦しみや悲しみから救い出してくれ、場合によっては私たちの災難を自らの身に引き受けてくれると言われています。
その姿はあたりまえのように私たちの日常に溶け込んでいますが、お地蔵様はすべての生命を優しく見守り続けているのです。
お地蔵さんの存在は、私たちが生きている間だけでなく、死を迎え、転生した後も続くと言われています。
仏教の教えによれば、死後の転生の世界は6種類存在し、それぞれに固有の困難や試練があるとされています。
しかし、どの世界に生まれ変わっても、お地蔵さんは変わらずに私たちに救いの手を差し伸べ、導いてくれると信じられているのです。
道祖神とお地蔵さんのつながり

お地蔵さんについて話す際、道祖神の存在が議論を複雑にしています。
道祖神とは、日本の古代から存在する、境界や十字路、三叉路など特定の場所に設置されていた魔除けの象徴です。
これは、悪霊や災難は外部から侵入するという考えに基づいています。
初期の魔除けは木の棒や岩など簡素なものでしたが、次第に石碑や彫像に発展しました。
例えば、『日本書紀』には、イザナギが黄泉の国から帰る際に境界に岐神を設置し、穢れを防いだとの記録があります。
また、道祖神は旅人や外から来た者を守る役割も果たしていました。
時間が経ち、旅人や遊女が道祖神を信仰するようになり、道や旅人を守る神としての特性が強まりました。
お地蔵さんには、この道祖神の特性を持つものもあります。
墓地の入り口にお地蔵さんがいるのは、生と死の境界を守っているからです。
無造作に道端に置かれたお地蔵さんも、旅人の安全と途中で亡くなった人の魂を守っています。
しかし、時が流れ供養されている具体的な人物が不明になったお地蔵さんには、悪霊が取り憑いている可能性もあります。
そのため、お地蔵さんと道祖神の区別がつかない場合、手を合わせるのは避けた方が良いでしょう。
まとめ
・確かに手を合わせるべきでないお地蔵さんが存在する
・道祖神の属性を持つお地蔵さんも、同様に手を合わせてはいけないケースがある
・お地蔵さんは慈悲深いが、それが故に悪霊などが寄ってくるリスクもある
お地蔵さんは無条件で全ての者を救済しようとする優しい存在ですが、それが逆に悪霊などを引き寄せる危険性もあります。
そのため、お寺や神社など、きちんと管理・祀られているお地蔵さんにだけ、手を合わせることを心掛けましょう。